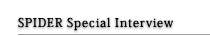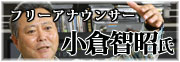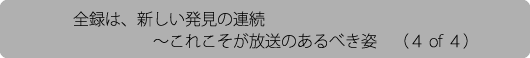
■ タイムシフトの次へ...
――となると、「全録」であるSPIDERは、これまでのビデオ機器でいうタイムシフトの概念から逸脱する機械なんでしょうか。
タイムシフトという概念は、'75-6年の段階でソニーが提唱したものです。その場にいなくても、違う時間にシフトしてみられる、ということで、それからのレコーダーでも、ずっとこの考え方が基本的になってきていました。
これが変わったのが2000年以降で、ちょうどこの頃はハイビジョン化やHDDレコーディングが始まった年でもあるのですが、そこからタイムシフトの概念が分化して、「コレクション」と「アーカイブ」が加わったわけです。
「アーカイブ」というのが死蔵させるコンテンツだとすれば、「コレクション」というのはよく見るものです。
 VHSは、それを一手に引き受けていたわけで、VHSの3倍モードで番組をアーカイブする人もいれば、一方で標準モードでコレクションする人もいた。
VHSは、それを一手に引き受けていたわけで、VHSの3倍モードで番組をアーカイブする人もいれば、一方で標準モードでコレクションする人もいた。
その後、ハードディスクレコーダーがでてくると、タイムシフトというのはハードディスクレコーダーの役割となり、録画したものの中から、大事なものだけをアーカイブまたはコレクションとしてディスクに書き出す、といった流れが生まれてきます。
――確かにそうですね。
では、「全録」がもたらす大きな変化は何かというと、これまでは、このアーカイブ、コレクションの総本山であった部分の変化です。これまで、この総本山の部分のハードディスクレコーダーはタイムシフトの道具でした。つまり、ターゲティングをしたコンテンツの集合体です。
これが「全録」機器に置き換わるということは、総本山がターゲティングする前のさまざまなコンテンツが詰まった集合体、コンテンツ・コンプレクスに変わる、ということだと思っています。
これこそが、タイムシフトに替わるまったく新しい概念になるんだと思います。これによってコレクションの価値もますます増してくるのではないかと期待しています。
――おっしゃる通りですね。(同じくこのインタビューに登場する)夏野さんは、そのコンテンツ・コンプレクスにある番組を番組表を使ってザッピングするのが楽しいとおっしゃっていました。
そういう楽しみ方もあるでしょうね。これまでのビデオ機器では、メーカーが与えたビデオ機器の使い方、つまり万人向けの使い方を、みんながしていたわけですが、全録の時代になると、1人1人が、自分の使い方を発見できる、というのも素晴らしさと思っています。
そうすることによって、番組もよりパーソナルになってくるし、より親密にもなってきます。
――ところで、「ビデオ・オン・デマンド」というのも、そうしたコンテンツ・コンプレクスに近い発想だと思うのですが。
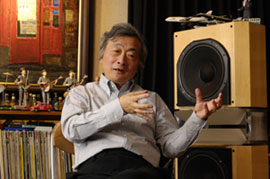 将来的にはNHKがNHKアーカイブスで言っているみたいに、ビデオ・オン・デマンドで、放送する側が番組を配信する時代が来るとは思っています。でも、僕はそれがユーザー的にはよくないと思っています。
というのは、ビデオ・オン・デマンドというのは、相手が主体なんですよ。つまり、「そこにあるか、ないか(用意するか、しないか)」というのは相手が決めることなんですよね。だから自分でコンテンツを手元に「置く」というのは、とても大事なんです。
将来的にはNHKがNHKアーカイブスで言っているみたいに、ビデオ・オン・デマンドで、放送する側が番組を配信する時代が来るとは思っています。でも、僕はそれがユーザー的にはよくないと思っています。
というのは、ビデオ・オン・デマンドというのは、相手が主体なんですよ。つまり、「そこにあるか、ないか(用意するか、しないか)」というのは相手が決めることなんですよね。だから自分でコンテンツを手元に「置く」というのは、とても大事なんです。
――確かにそうですね。「オン・デマンド」と言っていながら実は違うんですよね。
本当にそうなんですよ。「ビデオ・オン・デマンド」系の会社の方々と話をしてみると、月のうち何割かはコンテンツを入れ替えているというんですよね。
どんどんコンテンツを追加していくのではなくて、総量は同じで、よく見られるものから序列がついていて、あまり見られないものは消されてしまう。
でも、「見ないもの」というのは大多数の人がみないだけで、自分が見ないものじゃない。
だから、全部自分で持っておいて、再生するか再生しないか自分で判断する、というのが本当の自由だと思います。
いつもできる権利をもっているということが、放送を自分のものにするということなんじゃないかと思っています。それが全録では可能になります。最後に私の最新の本、アスキー新書「絶対ハイビジョン主義」の中にも、全録レコーダーの話がでてきます。ぜひ読んでくださいね(笑)。